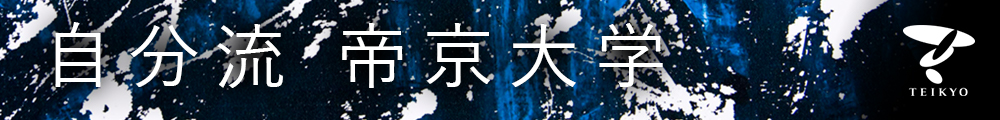地球カレッジ DS EDUCATION
自分流塾「最後の授業」 Posted on 2025/01/17 辻 仁成 作家 パリ
一つ気がかりなことは、どうやって人生を切り開いていくのか、ということである。
2年続いた辻ゼミだったが、今日、最後の授業となった。
生徒たちが卒業をするので、一区切りとなったのだ。
5人のゼミ生たちは、2年間、誰も挫けることなく、すべての授業に参加した。
ぼくのゼミは、特別ゼミと言われるもので、実は、単位もない、出席もとらない。無理しない範囲で参加してくれたらいい、という、緩やかなクラスであった。
ぼくがフランス在住なので、ほとんどが、通信回線を通しての授業となった。
にもかかわらず、体調を崩し登校できなくなった子でさえも、ぼくの授業にだけは、最後まで参加しつづけてくれた。
対面授業は一度しかできなかったが、フランスと日本、1万キロの距離をこえて、生徒たちに文学の一角を伝えることが出来たことは、ぼくの人生の中で、尊い期間となった。
ぼくは文学について、教えたりはしなかった。
ただ、彼らに小説の課題を出しただけ…。
たとえば「生きる」をテーマに30枚の小説を締め切り日までに書いてください、というようなものだった。
彼らはそれと向き合い、大学での生活の中で、忙しいだろうに、創作を続けた。
そして、「合評」と呼ばれることをやった。
一人の作品を、全員で、批評し合うのである。
褒められることもあるが、厳しく指摘されたり、批判されたりもする。
ぼくは、時々、だいたい最後の方に加わり、意見の交通整理などを行った。
その時、経験者でもあるわけだから、何が小説として成功していて、何がちょっと失敗しているのか、なんかを人生と絡めながら、語った。
文学的な手法で教えたことはない。
ちょっと違った角度で、つまり、物事の目線というのか、見方、感じ方、人間関係の意味とか、堅苦しい文法の話とかはなくて、どういう視点で、その世界を描いていくべきか、ま、見ていくか、というようなことを、だらだら、話した。
それを2年間、繰り返しやってきた。

彼らが、文学をどのように学び取ったのか、ぼくにはわからないが、少なくとも、彼らは30枚規模の短編小説を、何作も、提出してきた。
それは人生において、なかなかすごいことじゃないか、とぼくは思う。
たった10枚であっても、書くことは難しい。なのに、彼らはどんどん書いた。
そして、中には、数十枚にも及ぶ、長編を提出した者もいた。
若い学生たちとて、人間だから、希望を失い、意味がわからなくなり、やりきれない日々もあっただろう。
でも、諦めず、小説だけは提出し続けてくれた。
そこに彼らは何を見つけたのか?
書くことの喜びはあったかもしれない。
自分が創作したものを誰かが読んで意見を言い合う、という授業がそこにはあった。
つまり、自分の居場所があったのだ。
だから、彼らは休まず続けることができ、卒業していくことになった。
彼らの人生というものがどのようなものになるのか、ぼくにはわからないが、書くことの自信を身に着けることができたのじゃないか、と信じたい。
きっと、辛い時に、このゼミでの経験が、彼らの背中を押す。
のちの、人生に役立つこともあるだろう。
ぼくは、子供たちがのびのびと書いて発表しているあいだ、その背後にいて、笑顔で見ている牧人のような存在なのであった。

posted by 辻 仁成
辻 仁成
▷記事一覧Hitonari Tsuji
作家。パリ在住。1989年に「ピアニシモ」ですばる文学賞を受賞、1997年には「海峡の光」で芥川賞を受賞。1999年に「白仏」でフランスの代表的な文学賞「フェミナ賞・外国小説賞」を日本人として唯一受賞。ミュージシャン、映画監督、演出家など文学以外の分野にも幅広く活動。Design Stories主宰。