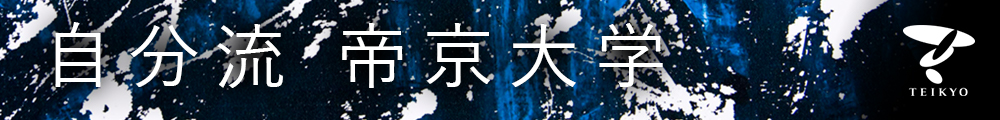欧州最新情報
パリ最新情報「食にも「社会保障」を。食費を支える新システム、フランス地方で広まる」 Posted on 2025/02/25 Design Stories
フランスの物価は日本に比べ、やはり高い。現在、フランスの消費税は20%だ。食品には軽減税率が設定されているとはいえ、コロナ禍やウクライナ侵攻の影響などで物価は上がり続けるばかり。食費をやむなく切り詰めるという家庭も、決して少なくない。
※フランスでは、生活必需品としてほとんどの食品に5,5%の軽減税率が適用されている。

こうした不安や格差を解消しようと、フランスの地方では「食の社会保障(la sécurité sociale alimentaire)」が試験的に導入されている。これは、医療健康保険制度にヒントを得たシステムで、毎月150ユーロ(約23,400円)が“食費”としてカードに支給されるというもの。食料を購入する店舗は自治体が決定するが、人々はBIOショップやマルシェやパン屋など、地域の提携店でこの支給金を使うことができる。つまり「食の社会保障」は、「保険証」のようなカードとなって、食費に限り月150ユーロまで使用できるという新しいシステムなのだ。
その目的は、長引く経済不安と闘い、人々に食べるものを選ぶ自由を取り戻すこと。長い目で見れば、農家の収入アップや地域経済の活性化につながる可能性もあるという。では、「食の社会保障」の財源はどこから来るのだろうか。
この保障制度は、50%が公的資金、25%が地方自治体、25%が利用者の負担金でまかなわれる。なかでも利用者の負担金は、それぞれの世帯の収入に応じて決まる。たとえば、もっとも収入の低い世帯では、毎月10ユーロ(約1,560円)が最低の負担額。一方で支給額は年齢や所得に関係なく、みな一律で150ユーロが支給されるという仕組みだ。

全国的な展開はまだ先かもしれないが、フランス南部の街モンペリエでは、この「食の社会保障」が2023年から導入され、利用者から好評を得ているという。
実際にカードを使用しているのは約400人と、まだ規模は小さい。しかし、利用者の購入品に関しては、その内容が明らかに向上したと報告されている。物価高で敬遠されがちなオーガニック食品を中心に、より質の高い食品を選ぼうとする動きが見られるそうだ。
もちろん、地元のBIOショップもこの制度の恩恵を受けている。フランスのBIOショップは「高い」という理由で客足が遠のき、インフレの影響で閉店が相次いでしまった。ところがモンペリエの店舗では、この制度のおかげで売り上げが2〜7%増加したと報じられている。

※その他にも現在、約40の自治体が「食の社会保障」を導入している
体に良いものを口にしたい、とは思っても、フランスの物価は2022年ごろから驚くほど上昇した。とくに生活に直結する電気代や食費は、毎期のように値上がりしている印象を受ける。オーガニック食品となると、通常商品の1.5倍から2倍の価格になるため、この部分の出費を削る家庭は多いだろう。
こうした背景もあって、「食の社会保障」に対するフランス人の反応は悪くない。ただし課題も少なからず残されている。例をあげると、提携店舗の多くが労働者階級の住む地域から離れており、自治体がこうした店舗ばかりを指定すれば、誰もが利用しやすいとは言えず「格差」の解消にはつながらない。
また、先日2月20日にはフランスの国会でもこの制度が審議されたが、時間不足のため採択されることも否決されることもなかった。ただ、ヤニック・ノイダー保健大臣は「財源的には難しい」としつつも、さらなる取り組みに前向きな姿勢を示している。

「食の社会保障」は、健康保険制度を参考にしながら、食を「すべての人が持つべき権利」として保障することを目指したシステムだ。もとよりフランスは、ヨーロッパ一の農業大国であり、食にかける情熱が大きい国。食費にも「保険」の考え方を導入するこの試みが、今後どこまで広がるのか注目したい。(や)